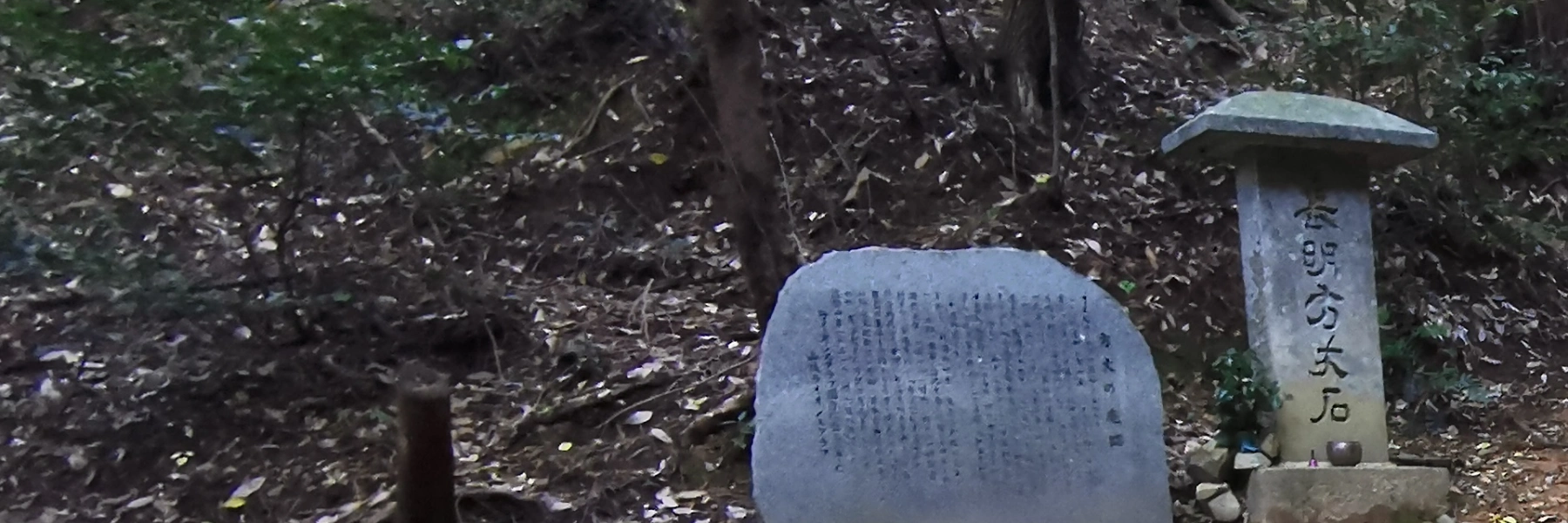-

枕草子「中納言参りたまひて」ポップな現代語訳と原文・語釈
「中納言参りたまひて」から始まる『枕草子』の段は、中納言こと藤原隆家が姉の中宮定子のもとを訪れ、「素晴らしい扇の骨を手に入れました!」と自慢げに話す一コマです。原文は主語がなく、誰のセリフかわかりづらいので、主語を付けてポップに現代語訳... -

無名抄「俊成自讃歌のこと(深草の里)」原文と現代語訳
無名抄「俊成自讃歌のこと(深草の里)」 俊恵いはく 原文・語釈 俊恵いはく、 「五条でたりしついでに、 『御らん』 と聞こえしかば、 語釈 俊恵:平安時代後期の歌人。鴨長明の師匠。 五条:藤原俊成のこと。藤原定家の父。 御:お住まい。お宅。 よそ... -

発心集第4-4「叡実、路頭の病者を憐れむ事」原文と現代語訳
発心集第4-4「叡実、路頭の病者を憐れむ事」 山に、叡実阿闍梨といひて 原文・語釈 山に、叡実びがたくて、 語釈 山:比叡山。 叡実:延暦寺の僧。生没年・伝記等未詳。 阿:天台宗・真言宗の密教僧の僧職の一つ。 帝:『続本朝往生伝』などによれば、第... -

紫式部日記「土御門邸の秋(秋のけはひ)」の原文と現代語訳
紫式部日記「土御門邸の秋(秋のけはひ)」 秋のけはひ入り立つままに 原文・語釈 秋のけはひ入がじし色づきわたりつつ、 語釈 入つ:(季節などが)来始める。立ちそめる。 土:藤原道長の邸宅。中宮彰子が出産のため滞在中。 梢:木の枝の先。 遣水:庭... -

方丈記(17)そもそも、一期の月影傾きて|原文・語釈・現代語訳
鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(17) そもそも、一期の月影傾きて 原文・語釈 抑たむとする。 語釈 そもそも【抑】:さて。 いちご【一期】:一生。生涯。 つきかげ... -

方丈記(16)衣食のたぐひ、また同じ|原文・語釈・現代語訳
鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(16) 衣食のたぐひ、また同じ 原文・語釈 衣食をあまくす。 語釈 ふぢのころも【藤の衣】:藤や葛の繊維で作った粗末な服。 あさのふ... -

方丈記(15)それ、人の友とあるものは|原文・語釈・現代語訳
鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(15) それ、人の友とあるものは 原文・語釈 夫を友とせんにはしかじ。 語釈 ねんごろ【懇ろ】:親しいようす。仲むつまじいようす。 ... -

方丈記(14)おほかた、この所に住みはじめし時は|原文・語釈・現代語訳
鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(14) おほかた、この所に住みはじめし時は 原文・語釈 おほかた、この所に住みはじめし時は、あからさまと思ひしかども、今すでに、... -

方丈記(13)また、ふもとに一つの柴の庵あり|原文・語釈・現代語訳
鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(13) また、ふもとに一つの柴の庵あり 原文・語釈 また、ふもとに一つの柴の庵す。 語釈 やまもり【山守】:山の番人。 かしこ【彼処... -

方丈記(12)その所のさまをいはば|原文・語釈・現代語訳
鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(12) その所のさまをいはば 原文・語釈 その所のさまを言はば、南に懸しからず。 語釈 かけひ【懸け樋・筧】:地上にかけ渡して水を...
よく読まれている記事